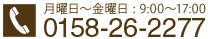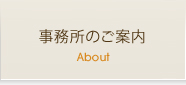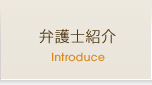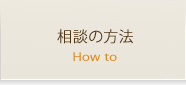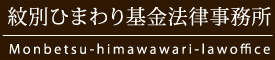リーガル通信 ~お年玉は誰のもの~
このコラムをご覧いただいている方の中には,お正月を迎えると,お子さんやお孫さんにお年玉を渡される方もいらっしゃるかと思います。諸説あるようですが,由来は鎌倉時代まで遡るほど,日本の伝統行事として定着していると言ってよいでしょう。
私たち弁護士が,お年玉のことでご相談を受けることはほとんどありません。しかし,インターネットなどを見ていると,「お年玉を親に勝手に使われてしまった!」といった子供からの悲鳴があがっていたりしています。そこで,このようなことに問題はないのか,あえて法的な観点から考えてみたいと思います。
まず,お年玉は,親(あるいは祖父母など)が子供にあげたもの(法律用語では「贈与」といいます。)です。そして,お年玉が子供にわたった時点で,その金銭は子供のものとなります。他方,民法では,親に子供の財産を管理する権限があることを認めています。ですから,子供にあげたお年玉を,親が子供からあずかり,これを親が管理することは法的には問題ありません。
もっとも,親に認められているのはあくまでも「管理」であり,勝手に使ってよいということではありません。生活が苦しいからといって自分の生活費にあてたり,自分の遊興費に使ってしまったりすると,財産管理権を濫用したと評価されてしまいます。この場合には,使ってしまったお年玉を子供に返還しなければなりません。また,子供の食費や教育費にあてることも,基本的にはNGでしょう。これらは基本的には,親のお金でまかなうべきものとされていますから,たとえ子供が習い事をしたいと言って,その月謝をお年玉から出すというのも,適切な使い方とは言えないでしょう。
もちろん,ご家庭の経済状況などで当面の資金が必要になる場面も出てくるでしょう。そういったときに,ご自身が管理しているお年玉を使ってしまいたくなる気持ちもわからないではありません。ですが,そういった必要性が生じた際には,使い道やその必要性などをお子さんにきちんと説明しておくことが大事でしょう。思わぬところで親子関係にヒビが入らないよう,気をつけていただければと思います。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第265号(2017/12/22発行)掲載
リーガル通信 ~離婚の慰謝料~
離婚のご相談を受ける際に多く聞かれるのが,「先生,相手から慰謝料を取れますか」ということです。今回は,離婚に際しての慰謝料についてお話したいと思います。
芸能人の夫婦が離婚する際に何千万円もの慰謝料を払ったという報道がたびたびされるため,みなさんの中には,離婚をする際には必ず相手から慰謝料を取れると考えている方も少なからずいらっしゃるかもしれません。しかし,実際はそうではありません。離婚をする際,相手に慰謝料を請求できるケースというのは,相手が「一方的に」夫婦の仲を破たんさせる原因を作った場合に限られます。たとえば,相手が不倫したことで離婚する場合,相手の暴力や暴言によって離婚する場合などがその典型です。これに対して,性格が合わないなどの理由で夫婦の意思疎通が欠けてしまい,結果として離婚に至ってしまうような場合は,どちらか一方に破たんの責任があるとは評価できません。性格が合わない相手に慰謝料を請求したいというお気持ちはわかりますが,このようなケースで慰謝料を請求するのは,法的には難しいでしょう。
また,相手に不倫や暴力などがあるケースでも,その事実を証明するものがあったほうがよいでしょう。相手が事実を認めた場合は別ですが,事実の有無で争いになった場合には,その証拠の有無で慰謝料をもらえるかどうかが変わってくるからです。暴力であれば,受けた傷の写真や病院の診断書などが証明の助けになりますし,不倫であれば,不倫相手とのメールなどが証拠となり得るでしょう。
では,慰謝料の請求ができるケースで相手からもらえる金額ですが,これはケースバイケースとしか言えません。ただし,最初にお話した芸能人のケースのように何千万円もの慰謝料を請求できるケースは極めて稀です。幅はありますが,百万円から三百万円までの間で落ち着くケースがほとんどだと思います。もっとも,相手に支払能力がなければ支払を請求することは難しく,このような場合は,分割で支払ってもらうか,基準よりも低い金額を支払ってもらうしかないことになります。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第263号(2017/11/24発行)掲載
12月12日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★
開 催 日 平成29年12月12日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*今回は都合により第3火曜日に行います。
12月7日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★
開 催 日 平成29年12月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
12月7日(木)★西興部村無料法律相談会(隔月第1木曜日)のお知らせ★
開 催 日 平成29年12月7日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
12月5日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★
開 催 日 平成29年12月5日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
リーガル通信 ~架空請求に注意!~
以前、架空請求に関する話題をこの欄でお話させていただきましたが、最近立て続けにご相談をお受けした件がありますので、繰り返しにはなりますが注意喚起をさせてください。
この1か月ほど、「民事訴訟管理センター」なる機関からハガキが届いたという相談を何件かお受けしました。このハガキは、総合消費料金が未納になっているなどとうたい、「民事訴訟としての訴状が提出された」「給与の差し押さえ及び動産物、不動産の差し押さえ」などと脅して不安を煽り、訴訟の取り下げについて相談するよう誘導しています。
法的な知識のない方がこのハガキをご覧になると、たとえ料金の滞納などに心当たりのない方でも不安になって、ついついハガキに書かれてある連絡先に問い合わせをしてしまうかもしれません。これが、何かの料金を払っていない方だとなおさら不安に思うことでしょう。
しかし、騙されてはいけません!
ハガキには不安を煽るようなことが多数記載されていますが、まず、本当に「訴状が提出された」場合、その訴状が訴えられた側に必ず届くことになります。このハガキ自体架空な請求ですから、裁判所から訴状が送られることはまずありませんが、心配な方は、問い合わせ先に連絡するのではなく、まず裁判所からの訴状の送付を待ってみてください。きっと送付はされませんから。
それから、「給与の差し押さえ」ですが、このハガキが届いただけで差し押さえになることはまずありません。差し押さえは一部の例外を除き、基本的には訴えられた後の判決が出るまではできないことになっていますから、ハガキが届いてもすぐに差し押さえになるなどということはありえません。
ですから、このような身に覚えのない請求には応ずる必要はありません。はがきが届いても無視することが大切です。
また、ハガキに記載された連絡先には決して連絡しないでください。電話などをしてしまうと相手に個人情報が伝わってしまい、繰り返しお金の請求をされることになりかねません。
不安になったり迷ったりした場合には、消費者センターや専門家にご相談することをお勧めします。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第261号(2017/10/27発行)掲載
11月21日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★
開 催 日 平成29年11月21日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*今回は都合により第3火曜日に行います。
11月7日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★
開 催 日 平成29年11月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
11月7日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★
開 催 日 平成29年11月7日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。